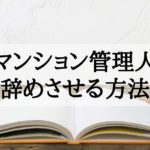マンション管理人の仕事は、定年退職後に運動も兼ねて、給料ももらえる気楽な仕事…というイメージは昔のことです。
本記事では、マンション管理業界は管理人不足のための対策を考えていますが、管理人が不足する社会的、業界的な背景を紹介します。
こんな方におすすめ
- 管理会社から管理員経費の値上げ提案を受けた管理組合の関係者(特に理事長・理事)
- マンション管理人の採用難、人材不足の状況を理解したい方
1 管理組合が知るべきマンション管理人が採用できず不足する背景
近年、管理人の不足、採用難という言葉を聞くことが多くなりました。
背景としては、これまで定年が60歳という企業が多かった中、大手企業を中心に定年を延ばしたことがあげられます。
また、ひと昔前の管理人さんと言えば、出勤後に少し掃除した後は、管理事務所でコーヒーと新聞を片手に受付を行い、住民と世間話をしていたという気楽なイメージだったかもしれません。
しかし、現実には、管理会社間の競争、マンション管理の適正化の推進に関する法律や個人情報保護の意識の高まりをはじめ、CS(お客様満足)の追求といったことで、覚えること、やるべきことはたくさん増えていますが、給与は最低賃金に近いという現状があることを管理組合理事会は知っておかなければなりません。
さらには、管理現場は体力的にきつく、汚い作業もあり、居住者からのクレームにもさらされます。
度を過ぎる管理員への要望
昨今増えている災害等の関係から「居住者の命を守る」という重責まで求められるようになっています。
管理人さんにも家族や守るべき人がいるにも関わらず、災害のときでも勤務しているマンションのことを優先しろという住民が本当にたくさんいることは驚きです。
つまり、これまで定年退職後は気楽に管理人でもやりながら小遣い稼ぎができたら良いという人が、仕事内容はもちろんのこと、給与や定年延長といった社会的背景により減ってきているのが現状です。
2 採用だけでは解決できない 管理人の不足に関するマンション管理会社の対策

このような状況において、管理人を派遣する管理会社では定年延長といった対応をしていますが、場当たり的なことでしかなく、問題の根本解決には至っていません。
また、管理人の主な業務である清掃では機械を導入すれば良いと思われるかもしれませんが、建物それぞれで形状が異なっており、結局導入コストが高くなってしまうような状況です。
そのため、これまで主流であった9時~17時に勤務するといった固定のシフトから、近隣マンションも含め、勤務時間を短くして複数を掛け持ちするケースを増やしていかなければなりません。
そうなると住民としては受付の時間が短くなることや清掃品質が下がることを受け入れなければならず、管理組合の合意形成も難しいです。
しかし、このような不自由(そもそも管理員がいないマンション管理という形も含め)を受け入れなければならない時代がすぐすこまで来ていることをマンション居住者は受け入れなければいけません。
3 人材不足・採用難のコストは管理員業務費に反映
管理会社としては最低賃金の増加や採用難に伴う採用コスト等の経費負担を委託費用(管理員業務費)に反映せざるをえない状況となっています。
これは最低賃金(参考に東京)が2009年は791円であったものが、2018年には985円と10年で25%増となっていることからも明らかにわかることです。※2019年にはさらに1,013円に上昇し、2020年はコロナ禍ということで据え置き。
しかし、例えば委託費用の内訳を見たときに、管理員業務費を勤務時間で割り戻した時給単価が1,200円であったとしましょう。
それでも、住民の中には「自分が知っているアルバイトより高く、ありえない、管理会社(派遣元)がその費用を吸収すべき」といった声を聞くことがあります。
管理会社に確認する必要はありますが、管理員業務費には管理人さんの社会保険料、交通費、ユニフォーム代、採用広告費、研修費といったものが含まれていることを忘れてはいけません。
この社会保険料だけでも単純に時給換算のプラス15%ほどが必要になります。
総合すれば、原価は最低賃金×1.3倍ほどになるので、良い人材を派遣してほしい場合は、それ相応の対価(東京の場合時間換算で1,500円以上)は、管理組合理事会として受け入れなければならない最低ラインと思わなければなりません。
いずれにしても管理組合理事会が社会的背景をしっかりと認識し、自分たちが求めるサービスを明確にして、新たな管理の方法を管理会社と協力して作り上げていく必要があります。
-

マンション管理人を辞めさせる方法~仕事をしない、偉そう、態度が悪い~
続きを見る
-

リプレイス市場が変わり始めた~管理会社が自ら撤退?~
続きを見る
-

マンションが管理会社を変更(リプレイス)する目的とメリット・デメリット
続きを見る